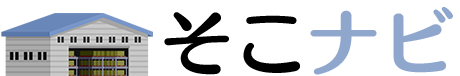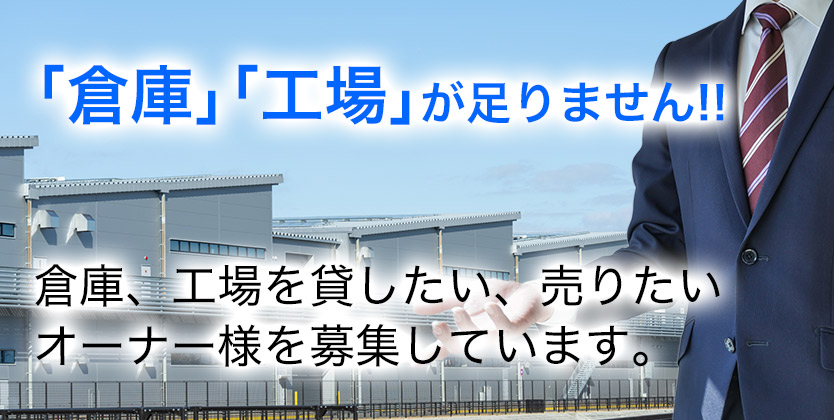「営業倉庫」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?
物流や商品保管の現場でよく耳にする言葉ですが、意外と詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、「営業倉庫とは?」という疑問に答えつつ、基本的な定義から種類、メリット・デメリット、選び方のポイントまでをわかりやすく解説します。物流業界に興味がある方や、ビジネスで倉庫を利用したいと考えている方に役立つ情報をお届けします。
営業倉庫の定義とは?
営業倉庫とは、簡単に言うと「他人の荷物を預かって保管し、お金をもらうための倉庫」のことです。もっと正確に言うと、倉庫業法という法律に基づいて国土交通大臣の登録を受けた倉庫業者が運営する倉庫で、第三者(他の会社や個人)の商品や原料を預かり、管理する施設を指します。
例えば、ネットショップの運営者が自社の商品を保管するために利用したり、製造業者が原材料を置いたりするのに使われます。
これに対して、「自家倉庫(または一般倉庫)」は自社の荷物だけを保管する倉庫です。自家倉庫は登録が不要で、自分たちのビジネスで自由に使えますが、他人の荷物を預かってお金をもらうことはできません。
営業倉庫は、他人の荷物を扱うため、法律で厳しく規制されているのがポイントです。
営業倉庫と自家倉庫の違い
営業倉庫と自家倉庫の主な違いまとめると下記になります。
| 項目 | 営業倉庫 | 自家倉庫(一般倉庫) |
| 目的 | 他人の荷物を預かり、保管料をもらう | 自社の荷物を保管する |
| 登録 | 倉庫業法に基づく国土交通大臣の登録が必要 | 登録不要 |
| 対象 | 第三者の商品・原料 | 自社の商品・原料 |
| メリット | 倉庫管理主任者の配置義務など専門的な管理が可能 柔軟に利用ができる |
コストが低く、自由度が高い |
| デメリット | 登録基準が厳しく、費用がかかる | 他人の荷物を扱えない |
営業倉庫は、荷主(荷物を預ける人)の利益を守るために、火災保険の加入が義務付けられています。一方、自家倉庫は建築基準法や消防法は守る必要がありますが、倉庫業法は適用されません。
例えば、大手通販会社が全国に倉庫を借りて商品をストックするのは、営業倉庫の典型例です。

営業倉庫の種類
営業倉庫は、保管する荷物の性質に合わせて大きく10の種類に分けられます。それぞれの倉庫は、倉庫業法施行規則で定められた設備基準を満たす必要があります。
以下に主な種類をリストアップします。
- 1.一類倉庫
最も汎用性が高く、日用品や繊維製品など幅広い荷物(第一類物品)を保管可能。耐火性能が優れています。 - 2.二類倉庫
燃えにくい第二類物品(例: 麦、塩など)を対象。防湿・防水設備が整っています。 - 3.三類倉庫
湿度や温度変化に強い第三類物品(例: ガラス製品、陶磁器など)を保管。設備基準が比較的緩やか。 - 4.野積倉庫
屋外で保管するタイプ。鉱物や土石などの雨風に強い荷物(第六類物品)向けで、堀や鉄条網で囲まれます。 - 5.貯蔵槽倉庫
円柱状のタンク型。第四類物品の穀物や液状物(例: 小麦、糖蜜)を大量に保管。 - 6.危険品倉庫
ガソリンや灯油などの危険物(第五類物品)を専門に扱う。消防法の厳しい基準をクリア。 - 7.冷蔵倉庫
-20℃以下、-20℃~0℃などで保管。生鮮食品や冷蔵品(第七類物品)向けで、-20℃以下のものは冷凍倉庫と呼ばれます。 - 8.水面倉庫
河川や海上に浮かべて保管。主に原木など(第九類物品)を対象。 - 9.トランクルーム
個人向けの小規模倉庫。家具や美術品など(第十類物品)を定温・定湿で保管。 - 10.特別の倉庫
災害救助など公共目的の特殊な保管
これらの種類は、荷物の分類(第1類〜第8類物品)に基づいて選ばれます。例えば、食品を扱うなら冷蔵倉庫が適しています。

営業倉庫の登録基準と関わる法令
営業倉庫を運営するには、倉庫業法に基づく登録が必要です。主な基準は以下の通りです。
- 施設設備基準
外壁の強度、耐火性、防火設備、防湿性能などが厳しく定められています。種類ごとに異なる基準があり、例えば一類倉庫は最も高い耐火性能を求められます。 - 寄託約款の届出
トラブル時の対応ルールを国土交通大臣に届け出る義務があります。 - 火災保険の加入
荷主の荷物を守るために必須。保険料は倉庫業者が負担します。 - 倉庫管理主任者の選任義務
倉庫ごとに1人、3年以上の実務経験または講習修了
無登録で営業すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また、関連法令として建築基準法、消防法、都市計画法などが適用されます。
営業倉庫のメリットとデメリット
メリット
- コスト効率:自社で倉庫を建てるより安く、必要な分だけ利用可能。変動する在庫量に柔軟対応。
- 専門管理:プロのスタッフが保管・発送を扱うので、品質が安定。自動化設備で効率化。
- リスク分散:火災保険付きで安心。複数拠点で災害リスクを分散。
- スケーラビリティ:ビジネス拡大時に簡単に容量を増やせる。
デメリット
- 費用:月額保管料や初期登録コストがかかる。長期利用でコストが積み重なる可能性。
- 依存性:業者に依存するので、倒産のリスクや業者ごとにサービスの差がある。
- 登録の手間:新規開設時は基準をクリアするのに時間と費用が必要。
例えば、小規模EC事業者にとって、営業倉庫は在庫管理の負担を減らす大きなメリットがあります。
営業倉庫を選ぶポイント
倉庫を選ぶ際は、以下の5つのポイントをチェックしましょう。
- 1.国土交通省の許可を確認:登録済みか公式サイトで調べる。無許可は避けましょう。
- 2.種類の適合性:保管する荷物に合った種類を選ぶ(例: 食品なら冷蔵倉庫)。
- 3.必要な資格の有無:食品や医療品の場合、温度管理資格や許可証を持っているか確認。
- 4.収容能力と柔軟性:現在の在庫量だけでなく、将来の増加に対応可能か。
- 5.追加サービスの充実:ピッキング、梱包、配送などの物流業務も委託できるか。
信頼できる倉庫業者を選べば、ビジネスの効率が大幅にアップします。

営業倉庫の最新トレンド
営業倉庫業界は「2024年問題」(物流の規制強化)の影響を受け、急速に変化しています。主なトレンドは以下の通りです。
- 自動化の加速
AGV(無人搬送車)やAMR(自律移動ロボット)、ドローン配送の導入が進み、人手不足を解消。 - DX(デジタルトランスフォーメーション)
IoTで在庫をリアルタイム追跡。倉庫管理システム(WMS)のAI活用で効率化。 - GX(グリーン・トランスフォーメーション)
環境対応として、太陽光発電やエコ素材の倉庫が増加。サステナブル物流がキーワード。 - 市場拡大
越境ECの需要増で、国際対応倉庫が人気。M&Aによる業界再編も活発。 - 課題解決
在庫管理の正確性向上やサプライチェーンの複雑化対策として、クラウド技術が活用されています。
これらのトレンドを取り入れることで、営業倉庫はよりスマートで持続可能なものになっていくでしょう。
まとめ
営業倉庫とは、他人の荷物をプロが管理する登録制の倉庫で、ビジネスに欠かせない存在です。種類を選び、メリットを活かせば効率化が図れます。2025年のトレンドとして自動化と環境対応が注目されています。この記事が、あなたの倉庫選びや理解の参考になれば幸いです。もっと詳しく知りたい方は、国土交通省の公式サイトをチェックしてみてください!
関東で営業倉庫を探している方はファクトリンクにお任せ下さい。
本サイト(そこなび)の関連サイト「そこなび+」でも多くの物件を掲載しております。